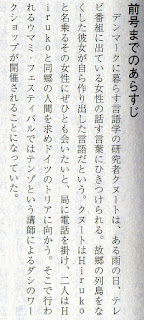どの世代までなら三一新書を覚えているだろうか?というのも、現在、三一新書を見かけないからだ。
実は発行元の三一書房では、1998年夏から長期労働争議があり、2011年に生まれ変わった。
従って、それまで発行されていた新書は、今は店頭にはない。同社のホームページに掲げられている新書は、いずれも2011年発行のものだけである。
まあ、それはともかく、人々が記憶している三一新書は、その年齢によって内容が違うだろう。
五味川純平の「人間の條件」は、第一部が発行されたのが1956年で、第六部で完結したのが1958年だから、今から約60年前になる。この頃10代後半からそれ以上であったとするならば、70代以上の人になるだろう。もちろん、1960年代、70年代に読んだ人もいるだろう。その人たちでも、多分、60代以上になっているだろう。
五味川純平の著作は、三一書房から出版されたものが多いが、新書として記憶に残っているのは「自由との約束」(全6部、1958~60年)、孤独の賭け(全3部、1962~63年)、「戦争と人間」(全18巻、1965~82年)ぐらいだ。「戦争と人間」を読んだという人は60代以上が多いだろう。
三一書房の編集者には、最初の頃は日本共産党の党員あるいはその支持者が多かったらしい。しかし、次第に党から離れ構造改革派に近寄り、一時は長洲一二など構造改革派のメンバーも多く出したらしい(新書No.272及び273「日本社会党」上下の著者である笹田繁は安東仁兵衛のペンネームであるという)。その後、新左翼に接近し、東大全共闘編の「果てしなき進撃」、秋田明大ほかの著作「大学占拠の思想」などの出版が続いた時期もある。これらを覚えているのも60代以上だろう。
日本消費者連盟編著の「あぶない化粧品」や「不良商品一覧表」、「合成洗剤はもういらない」、郡司篤孝の「危険な食品」などの企業告発(?)物を覚えているのは、50代以上だろうか?
こう見てくると、三一新書を覚えているのは、かなりの年齢になっていると言えるだろう。ただ、そのインパクトは結構あったような気がする。
この本に書かれていることで付け加えると、女性問題(?)に関するものも出しているという。石垣綾子の「女のよろこび」、上坂冬子の「私のBG論」などだ。
また、ミステリー・スパイものを含めた小説もある。たとえば三好徹の「風塵地帯」、邦光史郎の「夜の回路」などだ。
ゲリラに絡んで、ゲバラの「ゲバラ戦争」、「ゲバラ日記」、カルロス・マリゲーラの「都市ゲリラ教程」も新書になっているという。
書きおくれたが、この本の著者となっている井家上隆幸氏は元三一書房の編集者で、1958年の入社から1972年の退社まで、三一新書の編集にも携わった。この本はインタビュー形式であるが、著者のあとがきに依れば、インタビュアーは小田光雄という評論家・翻訳家らしい。時間の制約があったのか、著者の性格のせいなのか、あとがきに書かれているように、この本は『出版界の「歴史」を体験的に記録しようとする』、この”出版人に聞く”シリーズの意図からかなり逸脱し、”私的事情”をさらけだす始末になってしまっている。私が期待した、新書の編集理念や経緯などは、殆ど書かれておらず、表層的な時代ごとの傾向話になっていたのは残念であった。
因みに、見える範囲で私の本棚にある三一新書は、以下の3点であった。
日沼倫太郎著「現代作家案内 昭和文学の旗手たち」(No.574)
埴谷雄高編「内ゲバの論理」(No.829)
五味川純平著「戦争と人間16」(No.841)