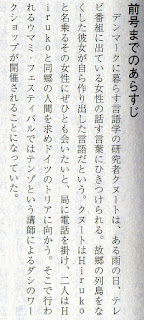「村上春樹以後ーアメリカにおける現代日本文学」都甲幸治(早大文学学術院教授、69年生まれ)
都甲幸治は翻訳者でもあり、村上春樹についても関心が深い。彼はこの稿で、日本文学に対して世界がどう見ているかを、具体的な内容をもとに論じている。
1)書店での売り上げ
(米国のアマゾンの日本文学トップ100ランキング:2017年9月12日アクセス)
1.遠藤周作「沈黙」(映画化の影響)
2.村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」
3.谷崎潤一郎「痴人の愛」
4.夏目漱石「こころ」
5.夏目漱石「吾輩は猫である」(電子版)
6.吉本ばなな「キッチン」
7.川原礫「ソードアート・オンライン」(第2巻)*ライトノベル
8.吉川英治「宮本武蔵」
9.吉川英治「宮本武蔵」(電子版)
10.紫式部「源氏物語」
都甲もいろいろとコメントはしているのだが、私はそれ以上にビックリのベストテンである。川原礫って誰、という感じだ。知らない。漱石や谷崎って、そんなに読まれているの。いくらサムライ文化に関心があると言っても、吉川英治を読むの。私は全くと言っていいほど読んでいない。
源氏物語も予想外だ。英語に訳してしまえば、口語と文語の壁は存在しないからだ、と都甲は書いている。ベスト100には、徒然草(17位)、枕草子(28位)、更級日記(70位)、松尾芭蕉「俳句集」(82位)、と古典文学が結構入っている。
近代文学は、
漱石:坊ちゃん(41位)、硝子戸の中(電子版)(68位)、草枕(81位)
谷崎:細雪(32位)、蓼喰う虫(39位)、短編集(55位)台所太平記(91位)
三島由紀夫:潮騒(18位)、午後の曳航(19位)、春の雪(26位)奔馬(53位)、真夏の死(59位)、禁色(76位)、金閣寺(97位)、
と意外と健闘している。
一方、現代文学は全く振るわない、と都甲は書く。
村上春樹:1Q84(36位)、風の歌を聴け・1973年のピンボール(45位)
吉本ばなな:みずうみ(71位) 多和田葉子:雪の練習生(24位) 嶽本野ばら:下妻物語(93位)
ミステリーでは、まるで日本のランキングのようだ、と言う。
横山秀夫:64(15位) 高見広春:バトル・ロワイヤル(37位) 東野圭吾:容疑者Xの献身(40位) 誉田哲也:ソウルケイジ(80位) 綾辻行人:Another(86位) 宮部みゆき:龍は眠る(87位)
ライトノベルでは、
アネコユサギ:盾の勇者の成り上がり(27位) 大森藤ノ:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(37位) 支倉凍砂:狼と香辛料(42位)、となっているが、私には全くわからない。
都甲曰く、アメリカでは3種類の日本文学愛好者がいる。すなわち、純文学愛好者、ミステリー愛好者、オタク系の読者。
2)英語圏の文学賞
純文学では、村上春樹が強いと言う。
「めくらやなぎと眠る女」で、2006年にフランク・オコナー国際短編賞受賞ほか、いくつかの賞で候補もしくは最終候補になった。
次には小川洋子。
「ダイヴィング・プール」で、2008年にシャーリー・ジャクソン賞受賞ほか、二つの賞で最終候補になった。
現在、評価を上げているのは川上弘美で、二つの賞で最終候補になった。
もちろん、大江健三郎も評価が高い、と言う。二つの賞で、候補、最終候補になった。
ミステリーでは、中村文則が特定の作品ではなく、貢献度でデイヴィッド・L・グーディス賞受賞(2014年)、鈴木光司が「エッジ」でシャーリー・ジャクソン賞受賞(2012年)、伊藤計劃が「ハーモニー」でフィリップ・K・ディック賞受賞(2010年)、円城塔が「セルフリファレンス・エンジン」で同賞を受賞(2013年)している。
3)新聞・雑誌の書評(英語圏)
村上春樹については、毀誉褒貶がある。小川洋子については、高く評価されている。多和田葉子の「雪の練習生」の扱いは破格である、という。水村美苗の「本格小説」については、日本文学の伝統と西洋文学の理想の二つをともに見事に実現していると評されている。村上龍の「オーディション」に対しては、フェミニズムが浸透している西洋では考えられない女性の描き方である、と評される。
ミステリーでは、横山秀夫、東野圭吾、湊かなえなどの作品について評されている。桐野夏生も読まれているが、中村文則の「王国」、「掏摸」や吉田修一の「悪人」が犯罪小説として売られる素地が英語圏にはできている、と言う。
4)雑誌・アンソロジー・小出版社
雑誌への掲載は、
「ニューヨーカー」(アメリカ):村上春樹20回以上、小川洋子2回、村上龍1回
二人だけではなく、次の作家たちも雑誌特集号やウェブサイト、アンソロジーで紹介されているという。
村田沙耶香、岡田利規、中島京子、小山田浩子、本谷有希子、星野智幸、藤野可織、島田雅彦、角田光代、黒田夏子、堀江敏幸、目取真俊、松家仁之、綿矢りさ、柴崎友香、古川日出男、川上未映子、平野啓一郎、松田青子、小野正嗣、窪美澄
アメリカでも村上春樹が他を押しのけて圧倒的な存在になっているのだろうという、先入観は、実際に調べてみると、上記のように見事に覆された、と結びに書いている。
(結論を要約するのは難しく、画像を参照願いたい)